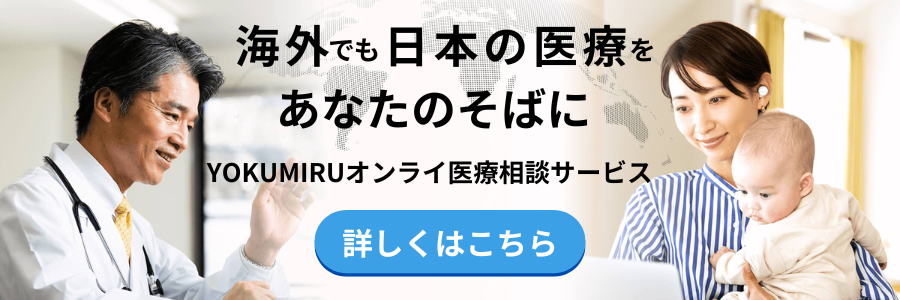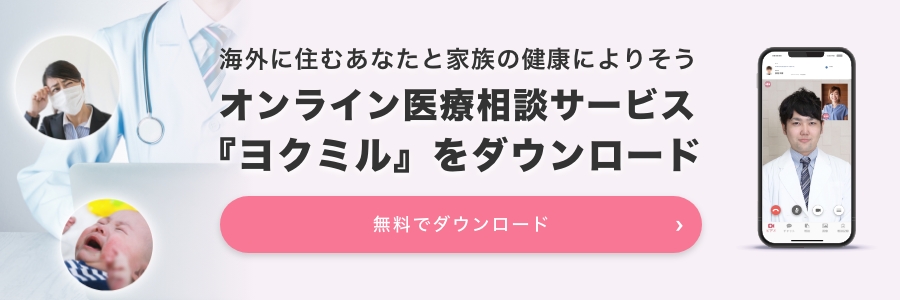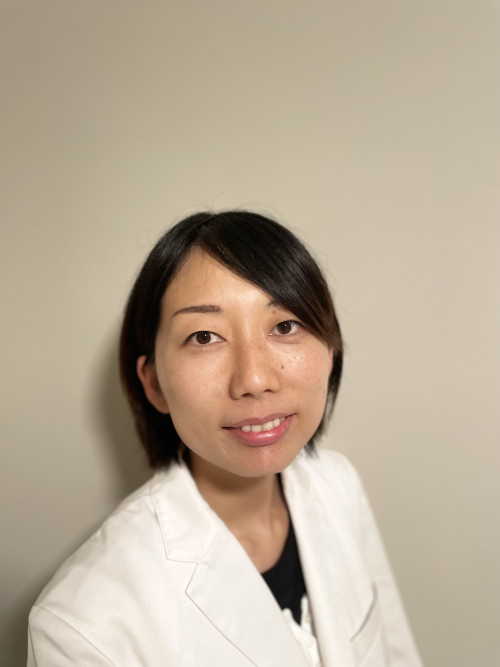「最近なんとなく疲れが抜けない」「気分が重くてやる気が出ない」など…
そんな心と体の不調、もしかすると「腸」が関係しているかもしれません。
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、脳と密接に影響し合っていることが分かってきています。
世界中の研究で注目されるこの“腸と脳のネットワーク”が、私たちの気分やストレス、疲労感にどう関係しているのか。
ここではその仕組みと、日常でできるセルフケアについて解説します。
腸は「第二の脳」気分にも影響する臓器
腸は食べ物を消化吸収するだけでなく、実は1億個以上の神経細胞を持ち、自律的に働いています。
腸内で作られる神経伝達物質のひとつ「セロトニン」は、気分を安定させるホルモンとして知られていますが、その約90%が腸でつくられていることをご存じでしょうか。
このため、腸の状態が乱れると、セロトニンの分泌が減り、「なんとなく気分が沈む」「やる気が出ない」といった心の不調につながることがあるのです。
腸と脳は、神経とホルモンでつながっている
腸と脳は「迷走神経」と呼ばれる神経や、ホルモンを介して常に情報をやり取りしています。
このネットワークは「腸–脳軸(gut–brain axis)」と呼ばれ、近年うつ病や慢性疲労、過敏性腸症候群(IBS)、炎症性腸疾患(IBD)などとの関連が注目されています。
たとえば、ストレスを感じると脳から「腸を緊張させる信号」が送られ、腸の動きが鈍くなります。すると腸内環境が悪化し、悪玉菌が増え、ガス産生や炎症を起こしやすくなる。
この腸内の不調がさらに脳にストレス信号を送り、気分の落ち込みや疲労を強める。まさに悪循環が生まれてしまうのです。

ストレス・食生活・睡眠が腸を左右する
腸内環境を乱す原因の多くは、私たちの生活習慣にあります。
・ストレス: 交感神経が優位になり、腸の蠕動運動(ぜんどう)が低下。ガスが腸内に貯まりやすく便秘や下痢が起こりやすくなる。
・食生活の乱れ: 高脂肪・高糖質な食事や不規則な食事時間は、腸内細菌のバランスを崩す。
・睡眠不足: 夜間の腸内細菌活動が低下し、炎症やホルモン分泌に悪影響を及ぼす。
「心の問題」に思える不調が、実は腸のコンディションと深く関わっているのです。
腸から整えるセルフケア
ちょっとした習慣の見直しでも、腸と心のバランスは改善していきます。
① 発酵食品を取り入れる
ヨーグルト・チーズ・コンブチャ・キムチ・納豆・味噌など、善玉菌が含まれる食品を日常的に。
② 食物繊維を意識する
野菜・海藻・果物・豆類を積極的に取り入れ、腸内で善玉菌が働きやすい環境を作りましょう。
③ 軽い運動をする
ウォーキングやストレッチは腸の蠕動を促進し、ストレス解消にも効果的です。
④ 睡眠の質を高める
腸内リズムは体内時計と連動しています。毎日の就寝・起床の時間を一定にすることが大切です。
⑤ 水分をしっかり摂る
腸の動きや排便リズムを整え、老廃物をスムーズに排出します。
医師に相談すべきサイン
次のような症状が重複して続く場合は、内科(消化器内科)やメンタルヘルスの相談を検討しましょう。
・便秘や下痢が2週間以上続く
・慢性的な疲労感や気分の落ち込みがある
・睡眠や食欲のリズムが乱れている
腸の検査や、食事・ストレス管理のアドバイスを受けることで、原因の見えない疲れが解消するケースも少なくありません。

まとめ
・腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、心と密接に関わる臓器
・ストレスや生活リズムの乱れが腸内環境を悪化させ、気分の落ち込みにつながる
・発酵食品・運動・睡眠などで腸から整える
・不調が続く場合は医師に相談し、腸と心の両面からケアを